

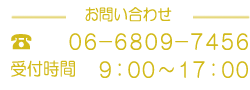
پ§530-0044 ‘هچمژs–k‹و“Œ“V–2’ڑ–ع9”ش1چ†ژلگ™ƒZƒ“ƒ^پ[ƒrƒ‹–{ٹظ11ٹK


ژ·•M

پs‰ü’ù‘•âپt
ژہ–±‚ة–ً—§‚آژذ‰ï•ںژƒ–@گl‚ج‰ïŒvٹîڈ€‚pپ•‚`
(‹¤’کپAگ´•¶ژذ)”ٹ§
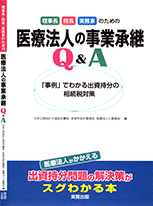
ˆم—أ–@گl‚جژ–‹ئڈ³ŒpQپ•A
(‹¤’کپAژہ–±ڈo”إ)”ٹ§

ژہ–±‚ة–ً—§‚آژذ‰ï•ںژƒ–@گl‚ج‰ïŒvٹîڈ€‚pپ•‚`
(‹¤’کپAگ´•¶ژذ)”ٹ§
‚¨‚·‚·‚ك
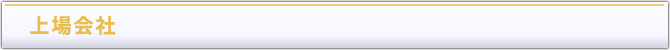
ژ„‚حپAŒِ”F‰ïŒvژm‚ئ‚µ‚ؤپA20”NٹشپA‘هژèٹؤچ¸–@گl‚إ‹à—Zڈ¤•iژوˆّ–@پiڈطŒ”ژوˆّ–@پjٹؤچ¸‹y‚ر‰ïژذ–@پiڈ¤–@پj‚ةٹî‚أ‚ٹؤچ¸‹ئ–±‚ةڈ]ژ–‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB
ژc”O‚ب‚ھ‚ç‹كچ ‚إ‚حپAٹؤچ¸گl‚جژw“±“I–ًٹ„‚حژم‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئٹ´‚¶‚ـ‚·پB
Œoچدڈîگ¨‚ةŒہ‚炸‰ïŒvپEگإ–±‚جگ¢ٹE‚إ‚àپAٹآ‹«•د‰»‚ح‚à‚ج‚·‚²‚¢گ¨‚¢‚إگi‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ج‚و‚¤‚بڈَ‹µ‰؛‚إ“Iٹm‚ة‘خ‰‚µ‚و‚¤‚ئژv‚¦‚خپA“Œں“¢ژ–چ€”‚ھگ¶‚¶‚ـ‚·پB
—ل‚¦‚خپA
پ@ٹؤچ¸‘خ‰
پ@![]() پ@ٹؤچ¸–@گl‚ضکb‚µ‚أ‚ç‚¢‚و‚¤‚ب‘ٹ’k‚â“ء’èˆؤŒڈ‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚جژQچlˆسŒ©
پ@ٹؤچ¸–@گl‚ضکb‚µ‚أ‚ç‚¢‚و‚¤‚ب‘ٹ’k‚â“ء’èˆؤŒڈ‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚جژQچlˆسŒ©
پ@گإ–±‘خ‰
پ@![]() پ@’P‚ب‚éگإ–±ڈˆ—‚إ‚ح‚ب‚پA‰ïŒvڈˆ—‚ًڈ\•ھ‚ة”Fژ¯‚µ‚½ڈم‚إ‚جٹضکAگ«‚ ‚éگ\چگ’²گ®
پ@’P‚ب‚éگإ–±ڈˆ—‚إ‚ح‚ب‚پA‰ïŒvڈˆ—‚ًڈ\•ھ‚ة”Fژ¯‚µ‚½ڈم‚إ‚جٹضکAگ«‚ ‚éگ\چگ’²گ®
پ@![]() پ@چ‘گإ’²چ¸‚ھچs‚ي‚ê‚é‚ئ‚«‚ج—ک_“Iڈ•Œ¾
پ@چ‘گإ’²چ¸‚ھچs‚ي‚ê‚é‚ئ‚«‚ج—ک_“Iڈ•Œ¾
پ@ƒOƒ‹پ[ƒv‰ïژذ“ٹ‡‘خ‰
پ@![]() پ@ƒOƒ‹پ[ƒv‰ïژذ‚ً‚ا‚¤“ٹ‡‚·‚é‚©‚جچؤٹm”Fپiژہچغ‚جŒo‰cڈمپA“à•”“گ§ڈمپAIFRSڈمپj
پ@ƒOƒ‹پ[ƒv‰ïژذ‚ً‚ا‚¤“ٹ‡‚·‚é‚©‚جچؤٹm”Fپiژہچغ‚جŒo‰cڈمپA“à•”“گ§ڈمپAIFRSڈمپj
پ@![]() پ@ٹا—–ت‚جژم‚¢“ء’è‚جƒOƒ‹پ[ƒv‰ïژذ‚ة‘خ‚·‚éژw“±
پ@ٹا—–ت‚جژم‚¢“ء’è‚جƒOƒ‹پ[ƒv‰ïژذ‚ة‘خ‚·‚éژw“±
Œں“¢ژ–چ€‚ھگ¶‚¶‚ؤ‚àپAژ–‘O‚ةٹؤچ¸گl‚ئ‘إ‚؟چ‡‚ي‚¹‚éٹآ‹«‚ھڈ‚ب‚‚ب‚èپAژ–Œم‚إ–â‘艻‚µ‚½ژ‚ة‚حژو‚è•ش‚µ‚ج‚آ‚©‚ب‚¢ژ–‘ش‚ةٹׂ邱‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
Œں“¢ژ–چ€‚ھگ¶‚¶‚½‚ئ‚«‚ة‰½‚إ‚àپuˆسŒ©Œًٹ·پv‚إ‚«‚é‘ٹژè‚ھ‚¢‚ê‚خپAˆہگS‚ةٹ´‚¶‚ç‚ê‚ـ‚·پB
ٹؤچ¸پiٹؤچ¸ژ葱پj‚àˆêگج‘O‚ئ‚ح‘ه‚«‚•د‚ي‚è‚ـ‚µ‚½پB
ƒٹƒXƒNƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ج“O’êپAٹؤچ¸’²ڈ‘‚ج“dژq‰»پAŒں“¢ژ–چ€‚ج’²ڈ‘‰»پAگRچ¸‘جگ§‚ج‹‰»پA•iژ؟ٹا—ƒŒƒrƒ…پ[‚ج‹‰»پAŒِ”F‰ïŒvژmپEٹؤچ¸گRچ¸‰ï‚جگ§’èپA“à•”“گ§ٹؤچ¸‹y‚رژl”¼ٹْƒŒƒrƒ…پ[‚ج“±“ü“™پXپB
ˆê”ش•د‚ي‚ء‚½‚ج‚حپA‰ïژذ‚جٹF—l‚ئٹؤچ¸گl‚ھ—¦’¼‚ة‚¨کb‚·‚é‹@‰ï‚ھŒ¸‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚إ‚·پBٹؤچ¸گl‚ج“ئ—§گ«‚ھ‹‚‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚àˆêˆِ‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپAگS—“I‚ب‹——£‚ھ—£‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ھپAچإ‚à‰e‹؟‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
ٹؤچ¸پiauditپAauditingپj‚جŒêŒ¹‚ح•·‚‚±‚ئ‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB
پuˆسŒ©Œًٹ·پv‚حپAپu’®‚پv‚±‚ئ‚©‚çژn‚ـ‚è‚ـ‚·پB
•sگ³ƒٹƒXƒN‘خ‰ٹîڈ€‚ھپA•½گ¬25”N4Œژ‚ةژn‚ـ‚錈ژZٹْ‚©‚ç“K—p‚³‚ê‚ـ‚·پB‚آ‚ـ‚èپA•½گ¬26”N3ŒژٹْŒˆژZ‚ةŒW‚éچà–±ڈ”•\ٹؤچ¸‚ھƒXƒ^پ[ƒg‚إ‚·پB
•sگ³ƒٹƒXƒN‘خ‰ٹîڈ€‚ج“±“ü‚ة‚و‚ء‚ؤپAٹؤچ¸ژ葱‚ھگV‚µ‚’ا‰ء‚³‚ê‚ـ‚·پB
‘ه‚«‚ب“ء’¥‚حپAپu•sگ³‚ة‚و‚éڈd—v‚ب‹•‹U‚ج•\ژ¦‚ًژ¦چ´‚·‚éڈَ‹µ‚ًژ¯•ت‚µ‚½ڈêچ‡‚ة‚حپAŒo‰cژز‚ةژ؟–₵گà–¾‚ً‹پ‚ك‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA’ا‰ء“I‚بٹؤچ¸ژ葱‚«‚ًژہژ{‚µپA‚»‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤ“üژ肵‚½ٹؤچ¸ڈط‹’‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤŒo‰cژز‚جگà–¾‚ةچ‡—گ«‚ھ‚ ‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ً”»’f‚·‚éپBپv‚±‚ئ‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µ‚ب‚ھ‚çپA“¯ٹîڈ€‚ج“±“ü‘O‚إ‚à•sگ³‚ة‘خ‚·‚éٹؤچ¸‹K”ح‚ح‚·‚إ‚ةچ‘چغ“I‚ة‘»گF‚ب‚¢‚à‚ج‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸‚إ‚·پB
چ،ŒمپAٹؤچ¸گl‚ة‹پ‚ك‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ح“‚»‚ج‹K”ح‚ً‚ا‚¤ژہچs‚·‚é‚©”‚·‚ب‚ي‚؟گE‹ئ—د—‚ج–â‘è‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB’P‚ب‚éƒmƒEƒnƒE‚ج–â‘è‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
“¯ٹîڈ€‚ج“±“ü‚ة‚و‚ء‚ؤٹؤچ¸ژہ–±‚ھچ¬—گ‚·‚邱‚ئ‚ھ—\‘z‚³‚ê‚ـ‚·پB
‘هگط‚ب‚±‚ئ‚حپAŒo‰cژز‹y‚رٹé‹ئ‚ج—کٹQٹضŒWژز‚àپA•sگ³‚ً‚ا‚¤‚·‚ê‚خ–hژ~‚إ‚«‚é‚ج‚©پA‚»‚ꂼ‚ê‚ج—§ڈê‚إ‰ü‚ك‚ؤچl‚¦‚邱‚ئ‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
copyright(C) 2012 Matsui-jicpa All Rights Reserved.